明治二分判金の価値と見分け方希少価値が高い逆打ちは7万円もの価値
今回は、明治二分判金の価値と見分け方についてご紹介を致します。 江戸時代に鋳造された二分判金は、文政二分判金(真文)・文政二分判金(草文)・安政二分判金・万延(まんえん)二分判金・明治二・・・Read More
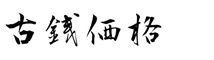

今回は、明治二分判金の価値と見分け方についてご紹介を致します。 江戸時代に鋳造された二分判金は、文政二分判金(真文)・文政二分判金(草文)・安政二分判金・万延(まんえん)二分判金・明治二・・・Read More
今回は、文政小判金(草文小判)の価値と見分け方についてご紹介を致します。 文政小判は、1819年(文政2年)から1828年(文政11年)にかけて11,000,000,000両以上も鋳造さ・・・Read More
今回は、寛永通宝の中から元文期(1736年から1741年)につくられた 十万坪 背十 をご紹介致します。 「十万坪」とか「背十」とかあまり聞きなれない言葉が続きますがひとつひとつ説明して・・・Read More
今回は、数ある寛永通宝のなかから「虎ノ尾寛」と呼ばれる寛永通宝の買取価格と見分け方をご紹介致します。 ちなみに、なぜ「虎ノ尾寛」と呼ばれるかというと、『寛』の13画目が虎の尻尾のように長・・・Read More
今回は、輸入銭の中から洪化通宝(こうかつうほう)という穴銭をご紹介致します。 「洪化通宝」ってあまり聞いたり見たりしないと思います。そのため、もしかすると価値があるのでは? なんて考えて・・・Read More
今回は、古銭コレクターに人気のある穴銭から「永楽通宝」をご紹介致します。 『永楽通宝』は、穴銭の一種で、その銭の中心には穴銭の特徴である正方形の穴が開いています。 また、銭・・・Read More
今回は、寛文8年(1668年)から享保2年(1717年)に鋳造された寛永通宝(新寛永銭)の取引価格と見分け方についてご紹介を致します。 ちなみに、寛永通宝は、寛永3年(1626年)から約・・・Read More
今回は、1944年(昭和19年)から発行された古紙幣をご紹介致します。 なじみのある紙幣が多いのですが、江戸幕末から昭和初期に発行された紙幣と違って市場価値が残念ながら低く高価な価格が期・・・Read More
今回は、江戸時代の後期から昭和初期までに発行された古紙幣の価値や買取価格についてご紹介を致します。 その前に! 小判や大判金には、金が含まれているので希少価値が高く、高値で取引されていて・・・Read More
今回は、日本銀行券のB号の中から板垣退助の100円紙幣の価値と見分け方についてご紹介を致します。 ちなみに、このB号とは、1950年から1953年に発行された紙幣で、「1000円」「50・・・Read More
今回は、政府紙幣の中からB号 板垣退助 50銭の価値と見分け方をご紹介をしたいと思います。 このB号とは、1950年から1953年に発行された紙幣のことで、今回ご紹介する板垣退助50銭・・・Read More
今回は、日本銀行券1円二宮尊徳の取引価格と価値についてご紹介を致します。 ちなみに、日本銀行券(日銀紙幣)とは、日本銀行から発行された紙幣で皆様も日ごろ使われている紙幣です。・・・Read More